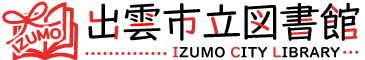図書館豆知識 59
| 質問 |
古代の火起こしの方法が知りたい。子どもに教えるので分かりやすいものが良い。 |
|---|---|
| 回答 |
古代の火起こしの方法として火溝式やキリモミ式があります。火溝式は木の板の同じ場所をひたすら木の棒でこするので、かなり体力が必要です。今回はキリモミ式をご紹介します。 準備するもの ①火種を落とすため、火きり板の隅に三角形のくぼみを刻む。その頂点に直径約15mmのくぼみを彫っておく。 |
| 参考文献 |
『今すぐ身につけたいサバイバルテクニック』(誠文堂新光社 発行) |
図書館の質問回答業務「レファレンス」を利用してみませんか。調べものや気になることは、気軽にお尋ねください。
※レファレンスには、宿題・課題、法律や医療相談、鑑定、個人のプライバシーに関わる調査など、図書館ではお答えできない内容もあります。ご了承ください。
※これまでに出雲市図書館で実際に受けた質問の中から一部を紹介します。(個人が特定できないよう、内容を一部編集・加工しています。)調べものの参考にしてください。